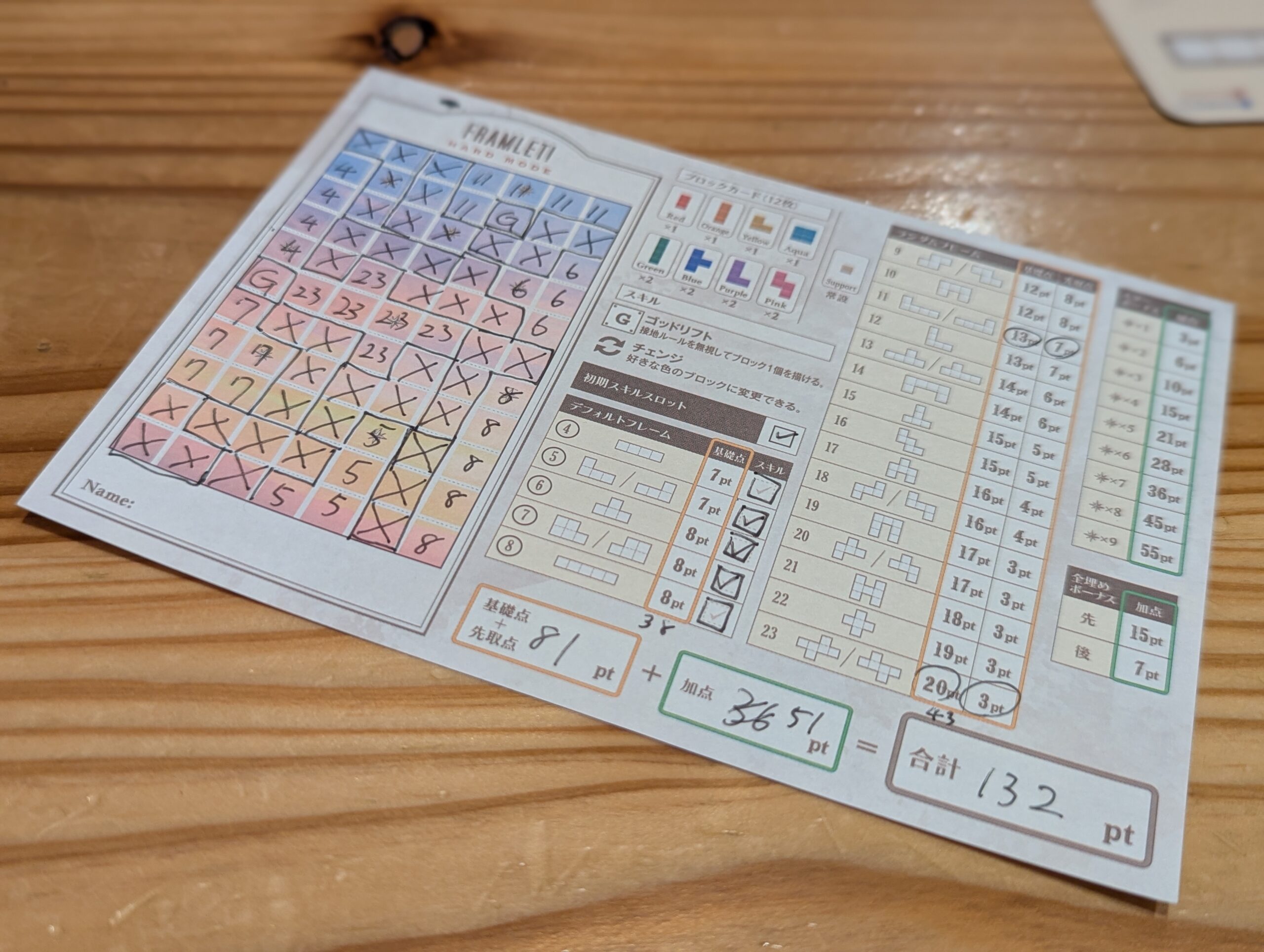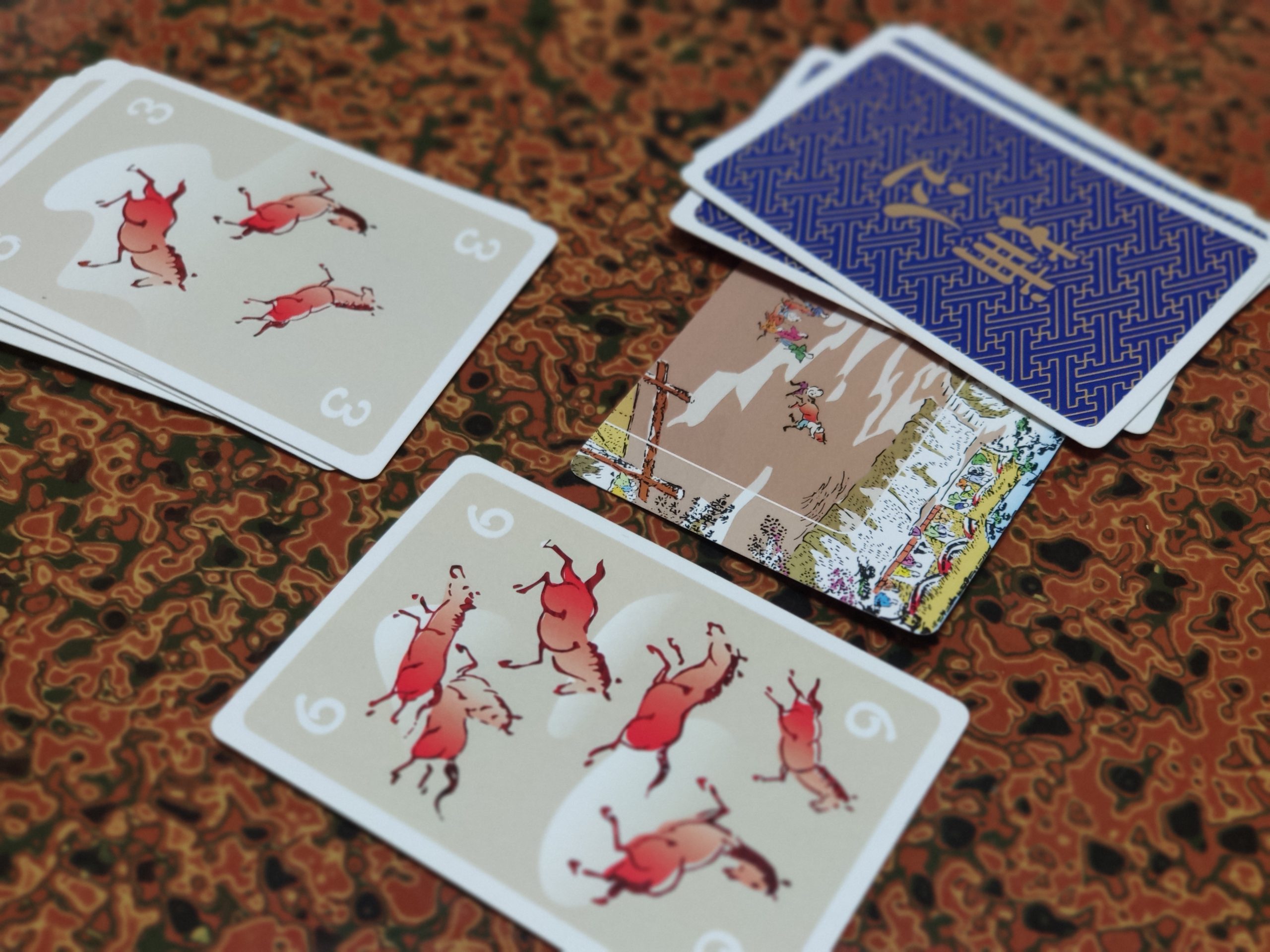評価:6/10
「リバイブ」の続編(?)。
エッセン新作。
大枠は似てるけど、端々が違っているので別のゲームとして捉えた方が良さそう。
アクションがカードメインでは無くて、スロットメインになっているが大きな違い。
6種類のスロットから1つのキーを差し込んでアクションが行う。
このメイン/サブ関係が「リバイブ」と逆になっているので、デッキビルド感は薄まり不平等感が無くなっている。
その分、種族能力&ガジェットでプレイヤー差が出るようになっている。
あと、トラックを進めることでNPC種族の能力を獲得できるようになっている。(「セティ」から影響を受けたと思われる)
あと、マップ構成が中央から四方に散る形から、下から始まって上に進んでいく感じに変わっている。
「リバイブ」を時代に合わせて調整してきた感じのゲーム。
全ての重量級好きゲーマーが楽しめる仕上がりになっている。
ただ、個人的には終盤のコンボの長さは爽快さよりも面倒さが勝ったので「リバイブ」の方が評価は高い。
エッセンの有名どころを大体遊べたので、個人的なエッセンランキングを記しておこう。
1. キングダム・クロッシング
2. テイク・タイム
3. アンツ
4. リコール
5. キーサイド
6. アヤ:太陽の子供たち
7. フェヤーズスワンプ
8. 天下
9. エドラのドルイド
10. パピリア
重量級ゲームはどれも一定以上の面白さはあるんだけど、最近では珍しい窮屈なプレイ感の「アンツ」、尋常じゃないまとまりの「リコール」、新しく破綻の無いシステムの「キーサイド」、ロピアーノがあの頃を取り戻しつつある「アヤ」あたりのインパクトが強かった!
カードゲーム系は、既に日本の同人ゲームの方が先を進んでいる感じはあるんだけど、そんな中唯一ランクインできたのは「テイク・タイム」。相談して作戦を立てるっていうアナログゲームっぽい部分に着目していて、我々がボードゲームに何を求めていたのかを思い出させてくれた。
「キングダム・クロッシング」は、1時間に過不足無くトレンドの要素を詰め込みつつ、「一筆書きムーブ」っていう軸をブラさず調整できるていて完璧!
去年のエッセンランキングはタイミングを逃して載せれてなかったけどメモが残っていたので、とりあえず掲載しておきます。
1. スチームパワー
2. セティ
3. シヴォリューション
4. イノリの谷
5. エンデバー:ディープシー
6. シャクルトン・ベース
7. ロアリング・トゥエニーズ
8. スペキュタキュラー
9. インジーニアス3D
10. 7エンパイア