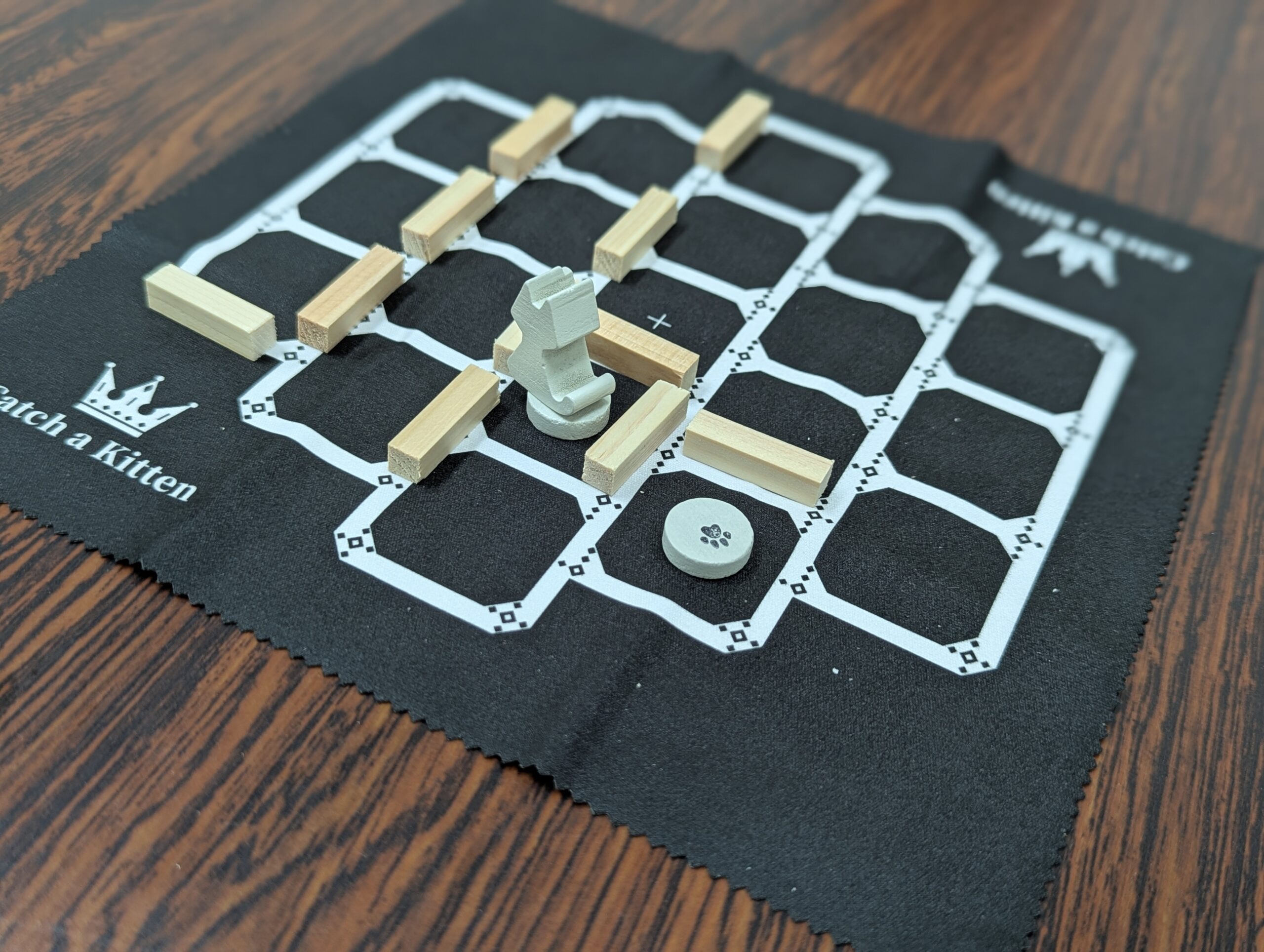「オレンジとレモン」という童話をモチーフにしたボードゲーム。
「ロンドン大火」のデザイナー。
ワーカー配置とアクション実行のフェイズが分かれているタイプのワーカープレイスメント。
アクションを実行した順がそのまま、次の手番順になる。
「キングドミノ」式手番順システムをワーカープレイスメントに適用したのは初めて見たかも。
色んな得点要素があるんだけど、そのほとんどにマジョリティ点をつけることで特化戦術にブレーキを掛けている。
これも単純だけど、うまく作用していて他プレイヤーの動向を注視する必要がある。
派手なシステムがあるわけじゃないけど、手堅くまとまっている。
ボーナスタイルのめくり運が悪い時の救済が無いのは気になったけど、当時の貿易のギャンブル性を表現しているってことでご愛敬かな・・・