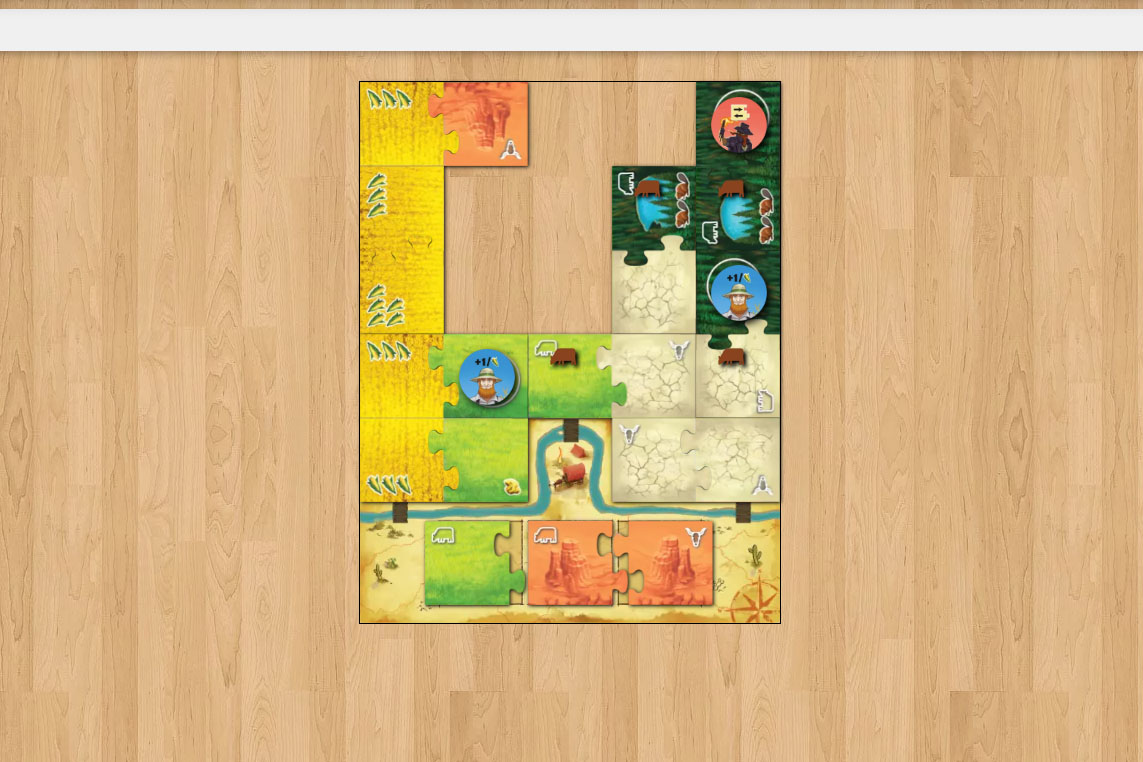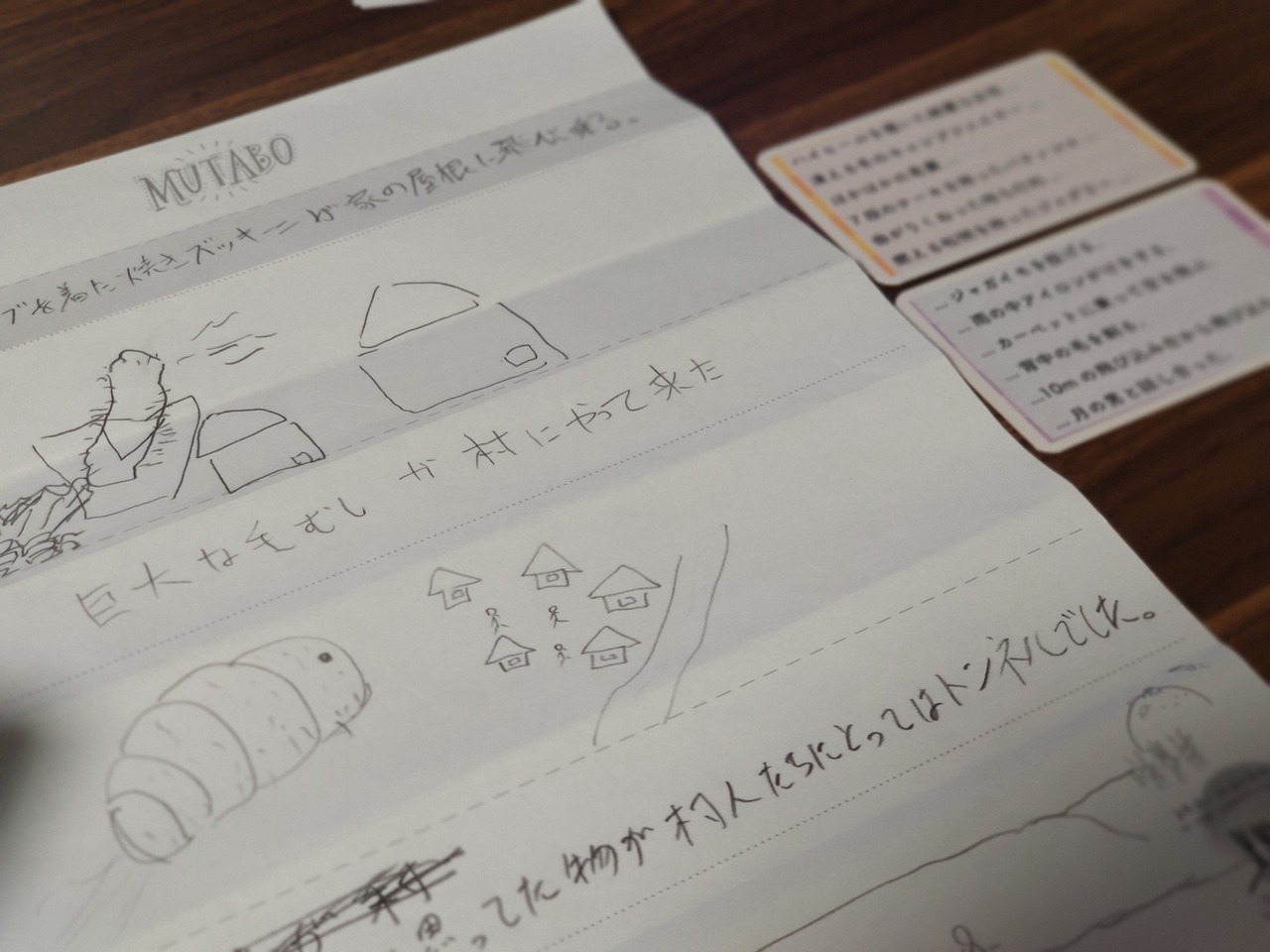全員が同じロケットに乗って、遠くの惑星を目指す。
クニツィアの作った「クラウド9」。
BGAでプレイ。
1人がキャプテンになって、他のプレイヤーはいつ降りるか判断!ってのいうのは同じ。
カードを持っているかどうかのブラフ要素は無くなり、純粋にダイスロールでバーストするか否かに賭ける感じになっている。
マスごとに使えるダイス目が記されていて、使えるダイス目が一個も出なかったらバースト!
使えるダイス目が出たら、使う目を選んで、その目のダイス全てを消費して、出目合計だけ前進する。
これだけだと、全員フラットで面白く無いので、乗組員毎に特殊能力を持っている。
キャプテンから順番にどの乗組員を乗せるかを決めていくので、キャプテンがやる気ありそうなら、相乗りで良い乗組員を乗せたり、逆に妨害しやすい乗組員を乗せたりする。
「クラウド9」よりも起伏があって面白い!
が、個人的にダイスバーストは苦手なジャンルなので、この評価。
オンラインだとダイスロールが素っ気ないのもマイナスに働いたかも・・・