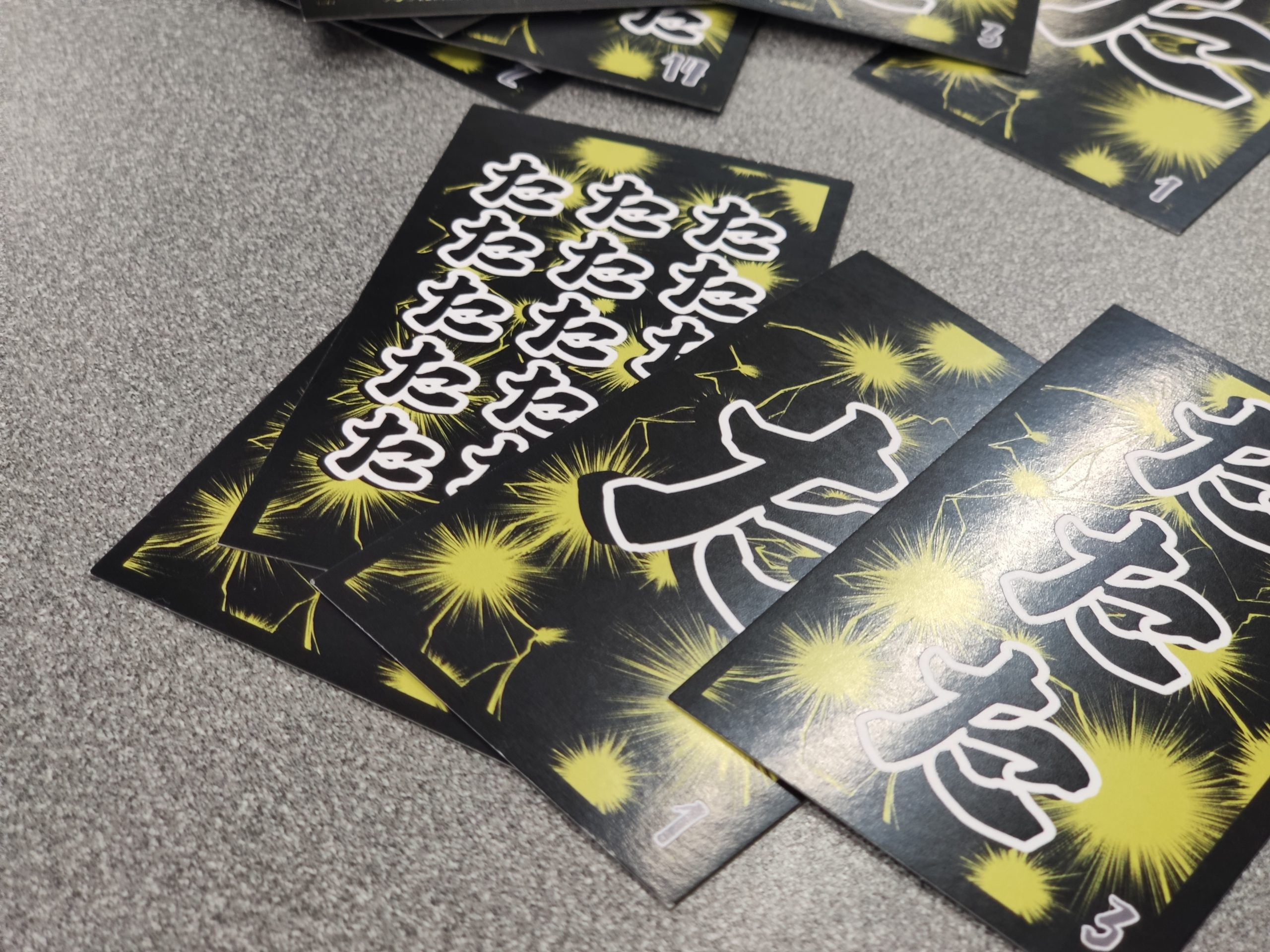評価:6/10
5色の列で綱引きを行う2人用ゲーム。
「キャッスル・コンボ」のデザイナーコンビ。
今年のKDJ推薦リスト入り。
手番では手札から1枚をプレイするだけ。
カードの使い方が3種類ある。
1つ目は最も分かりやすい「カードコストを払ってカード効果を起動」。
カード効果はトークンを自分側に引き寄せるのがメインだけど、色々な効果がある。
高コストのカードほど効果も強くなっていて、特に9,10コストのカード効果は膠着を打開する強力な効果となっている。
カードは対応する色の列の自分側に配置される。
永続効果といった物は無くて、重要なのは置かれている枚数。
以降、置かれている枚数分だけ、その色のカードコストが割引される。
シンプルながらゲームをドライブさせる良いルールだ。
2つ目は技術トラックの前進。
出したカードに示された種族のトラックを進められる。
これを行うにはカードとは別にゼニシウムという高価値リソースを支払う必要がある。
トラックを進めることでボーナスが貰えるのだが、進むとそれまでのボーナスを全て獲得できるので特化させると強烈な効果を生み出す。
3つ目はおまけボーナス。
出したカードに示された種族に応じた、ちょっとしたボーナスが貰える。
他と比べると弱いボーナスなので出来るだけ使いたくないけど、手詰まった時には仕方無いって感じかな。
見た目から特殊能力バチバチの殴り合いゲームかと思っていたんだけど、能力は厳選されていて、かなり面白い!
綱引きゲームなので、序盤は中々得点できないのだが、互いの状況が整ってくると一気にゲームが動き始める。
2人プレイ以外に4人のペア戦もある。
チームの2人が連続して手番を行うのだが、各自担当列が2列ずつ決まっていて、残り1列はどちらもアクセスできる列になっている。
3つ目のおまけボーナス実行で手札をパートナーに渡すことができるので、2人プレイよりも価値が上がっている。
ペア戦ならではの面白さがあって、こちらも面白い!
ちょっと見た目のB級感が強いけど、中身は一級品なので2人用ゲームが好きな人は遊んでみてほしい。